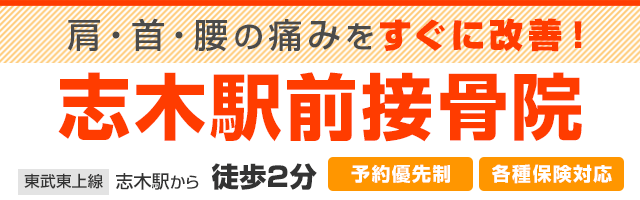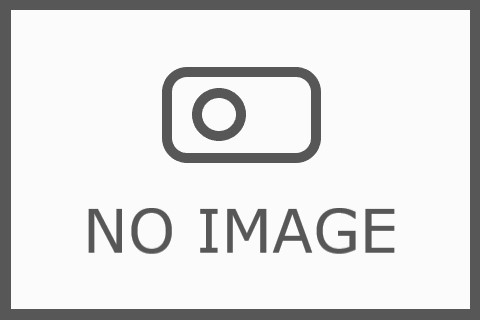オスグッド

こんなお悩みはありませんか?

膝の痛みで正座ができない
歩くだけでも痛い
階段の昇降で痛みを感じる
膝の皿の下あたりが腫れていたり、押すと痛い
運動後に痛みが強くなる
オスグッドについて知っておくべきこと

オスグッド病は、成長期のお子さまに多く見られるもので、膝を伸ばす動作を繰り返すことによって発症することが多く、膝のお皿の下にある骨(脛骨粗面)が隆起し、腫れや痛みを引き起こすことがあります。
そのため、部活動やクラブチームで運動をしている学生の方や、急激に身長が伸びる成長期のお子さまなどに起こりやすく、どなたにも起こり得る症状といえます。
ほとんどの場合、成長が終わると痛みは落ち着いていきますが、無理をしてしまうと成長期が終わった後にも痛みが残ることがあります。そのため、発症後はしっかりと休息を取り、適切なケアを受けることが大切です。
症状の現れ方は?

オスグッドの症状の現れ方として、主なものは以下のとおりです。
・膝のお皿の下あたりに痛みや赤み、熱感、腫れがある
・スポーツをすると痛みが出て、休むとおさまる
・膝の下の骨(脛骨粗面)が突出してくる
・膝を曲げると痛みを感じる
このような症状は、急に現れる方もいらっしゃいますので、どなたにも起こる可能性があります。
成長期のお子さまに多く見られるオーバーユース障害(膝などの使いすぎによる疾患)のひとつであり、特にバスケットボールやサッカーなどのスポーツを活発に行っている、10歳から15歳のお子さまに多くみられます。そのため、該当する方は注意が必要です。
その他の原因は?

オスグッド病で痛みが出る部分は、「脛骨粗面(けいこつそめん)」と呼ばれる、すねの骨の一部です。
膝関節を伸ばす際には、太ももの前側にある「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」が使われます。大腿四頭筋は、膝のお皿(膝蓋骨)を経由して脛骨粗面に付着しています。
脛骨粗面を含め、子どもの骨には「成長骨端線」という、骨が成長するための部分があります。成長期に、この脛骨粗面の骨端軟骨へ過度な牽引ストレスがかかり続けることで、骨端部の成長が妨げられ、徐々に痛みや変形といった症状が現れることがあります。
スポーツのあとに適切なケアを行っていなかったり、それを怠ってしまったりすると、症状が強くなるケースもございます。日頃から丁寧にケアを行うことが大切です。
オスグッドを放置するとどうなる?

オスグッド病を放置すると、以下のような問題が生じる可能性があります。
・痛みが強まり、大人になってからも違和感が残る場合がある
・骨や軟部組織に成長の異常を引き起こすことがある
・膝の可動域が狭くなり、しゃがむ動作などが思うようにできなくなることがある
・膝に変形が見られることがある
・成長に影響を及ぼす可能性がある
このように、痛みが続いたり、変形につながるケースもあるため、将来的な生活にも影響する可能性があります。放置せず、早めにケアを行うことが大切です。
当院では、施術に加えて、日常生活でのケア方法や予防のための指導も行っております。お困りの際は、ぜひ一度当院へご相談ください。
当院の施術方法について

当院では、最初に指圧と温熱による施術を行い、体内の血流を促進していきます。血流が良くなることで、筋肉の緊張が緩和され、痛みの軽減が期待できます。
自費での施術では、「筋膜ストレッチ」をおすすめしております。筋膜ストレッチを行うことで、筋肉がしっかりと伸ばされ、柔軟性が向上し、緊張の緩和や症状の軽減が見られることがあります。
また、筋膜ストレッチ以外にも、「アイシング」による患部の冷却で炎症を抑える方法もございます。患部に熱感がある場合や、腫れていると感じるときには、アイシングを用いたケアをおすすめしております。
さらに、「EMS(電気施術)」もご用意しております。EMSは電気の刺激によって、患部周辺の筋肉へアプローチし、症状の早期軽減が期待できる施術方法です。
改善していく上でのポイント

オスグッド・シュラッター病は、成長期のお子さまや若年層に多く見られる、膝に痛みを伴う症状です。症状の軽減を目指すためには、いくつかのポイントを意識することが大切です。
まず、適切な休息を取ることが重要です。痛みがある場合には、無理に運動を続けず、膝をしっかり休ませることが必要です。次に、アイスパックを使用して炎症を抑える方法も、症状の軽減が期待できます。
痛みが落ち着いてきたら、ストレッチや筋力トレーニングを行い、太ももやふくらはぎの筋肉を整えていくことが推奨されています。
さらに、適切な靴の選択も大切なポイントです。クッション性がある靴や、自分の足に合ったサイズの靴を選ぶことで、膝への負担をやわらげることができます。また、運動前のウォームアップや運動後のクールダウンを丁寧に行うことで、柔軟性を保ち、予防にもつながります。
そして、必要に応じて専門機関での診断を受けることも忘れずに。場合によっては、理学療法などのサポートを受けることで、より効果が期待できることもあります。
これらのポイントを日常的に意識して取り入れることで、オスグッドの症状の軽減が期待されます。
監修

志木駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:千葉県松戸市
趣味・特技:車中泊旅行、野球